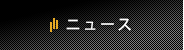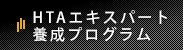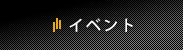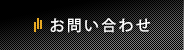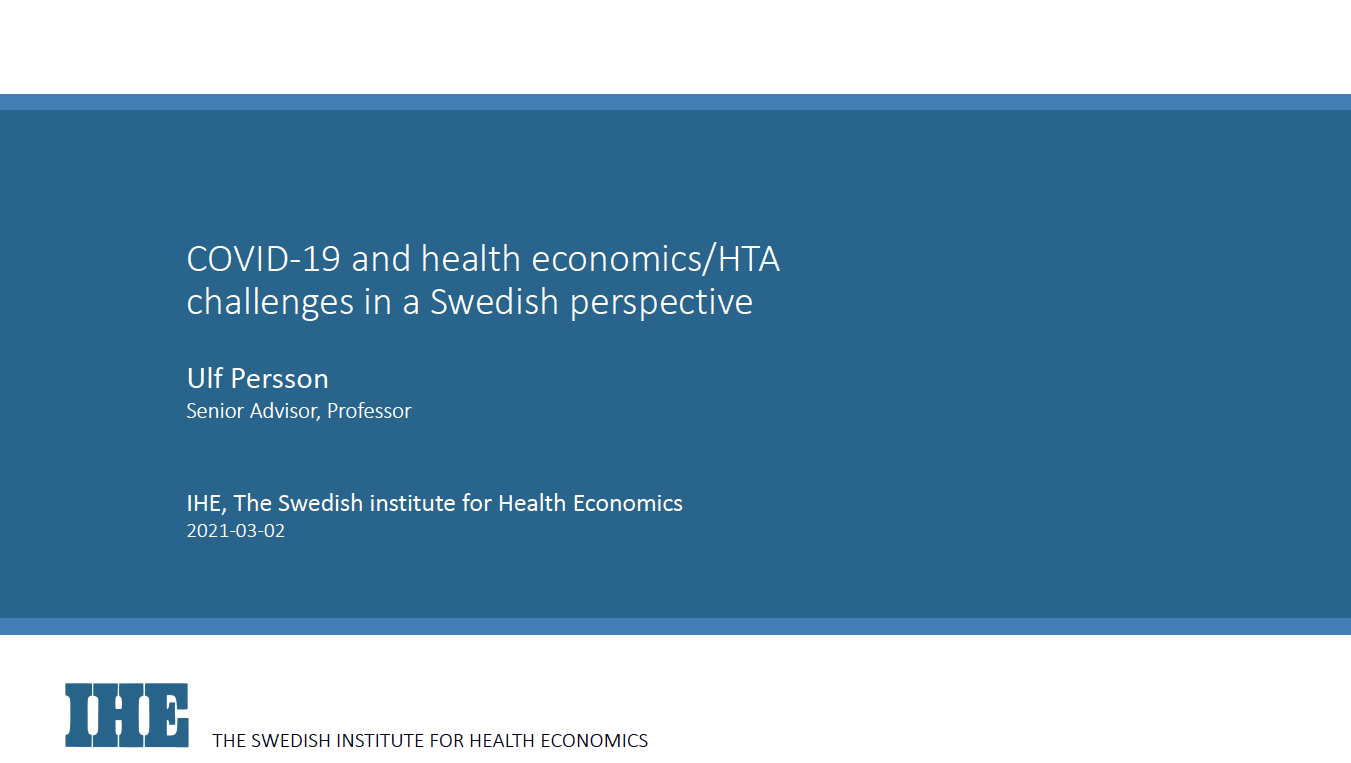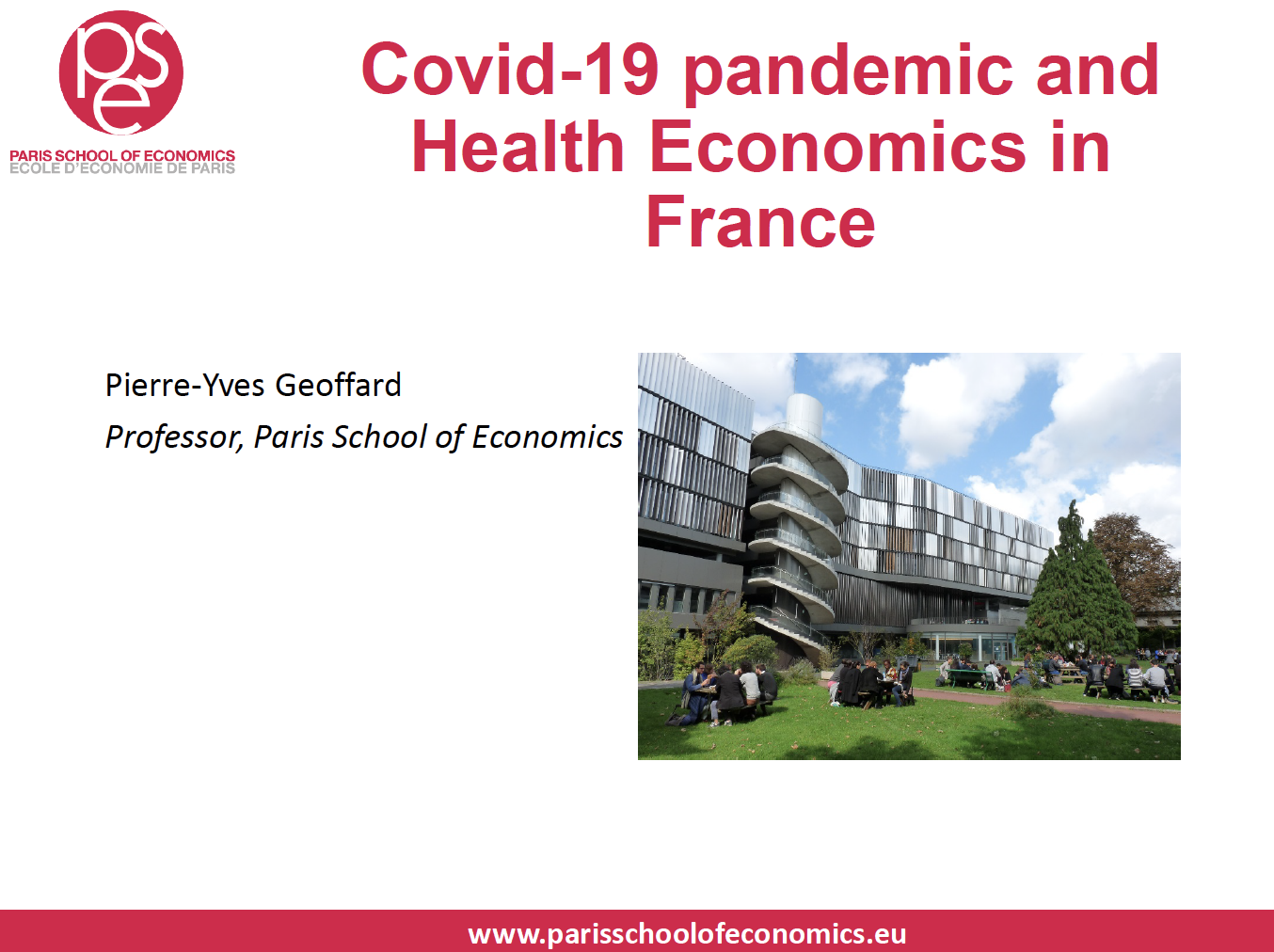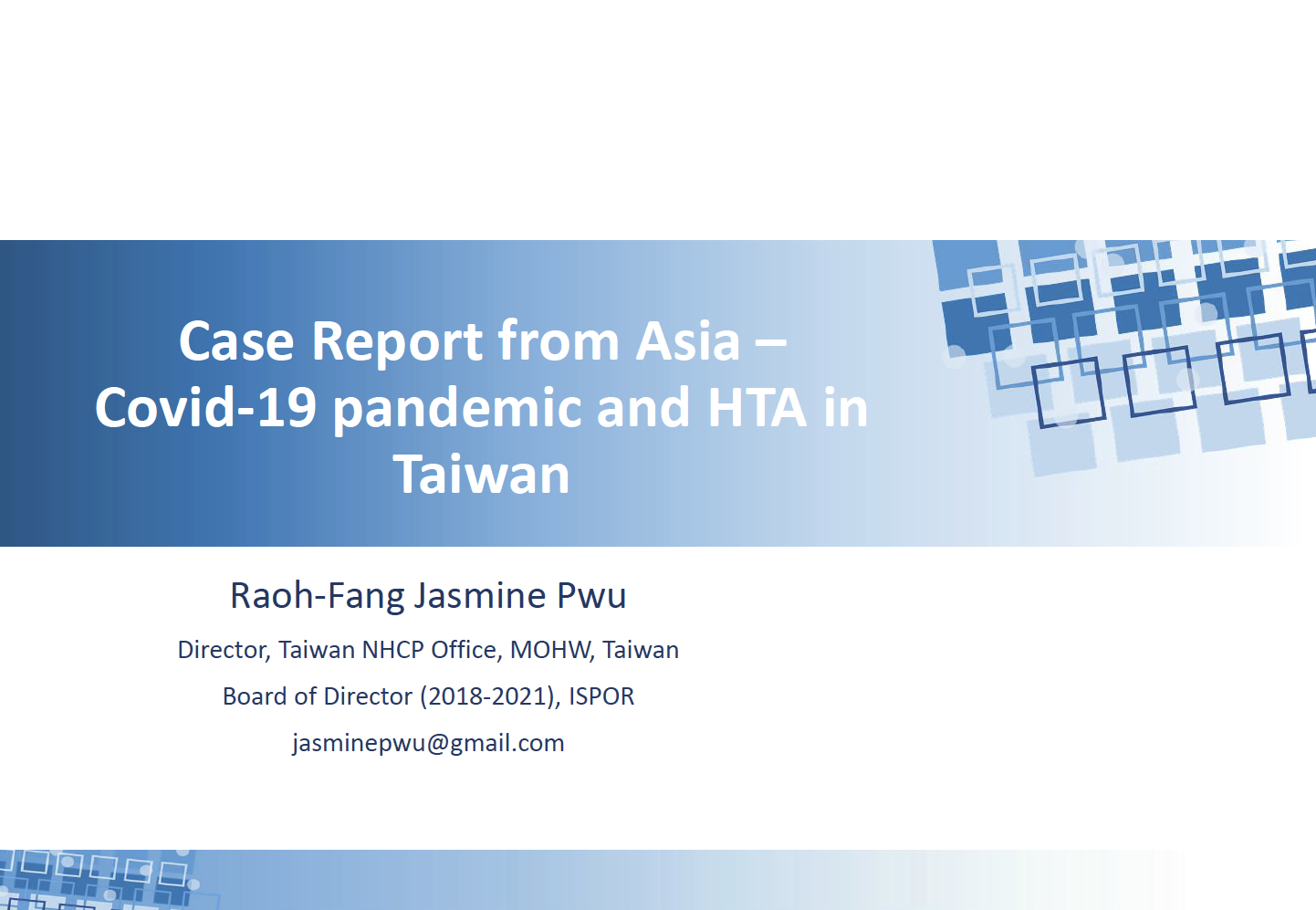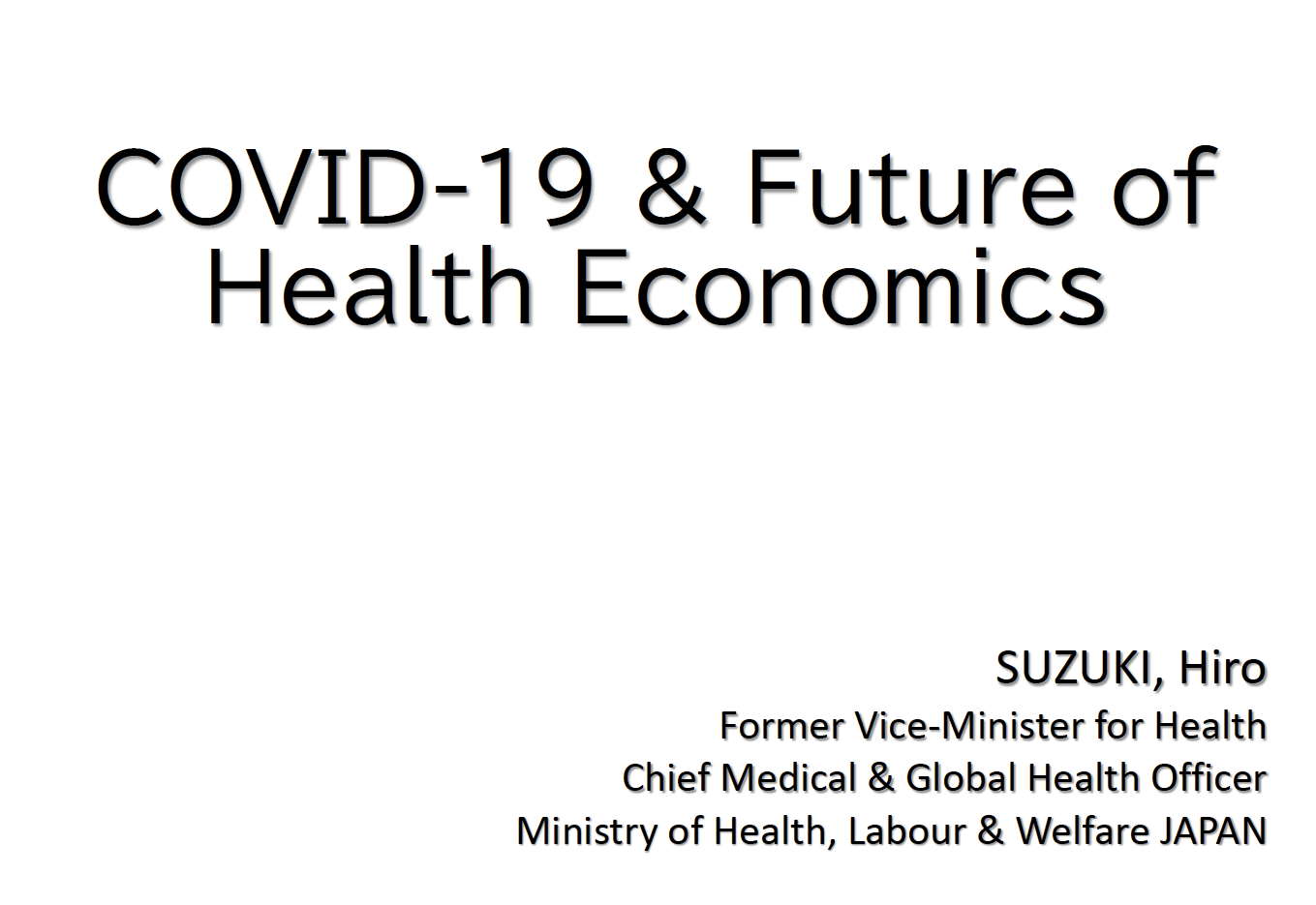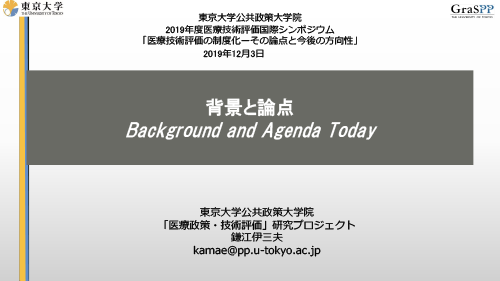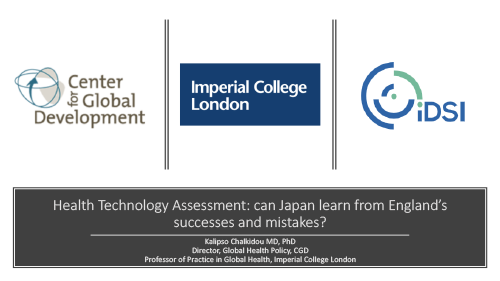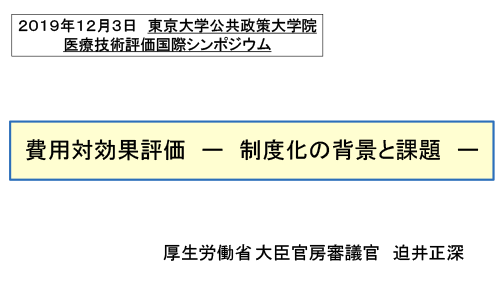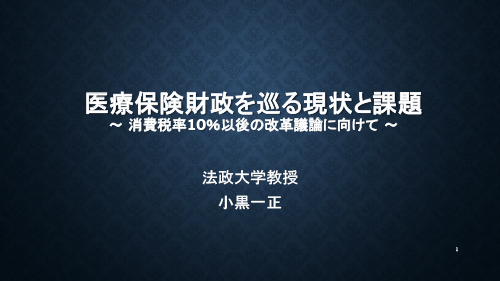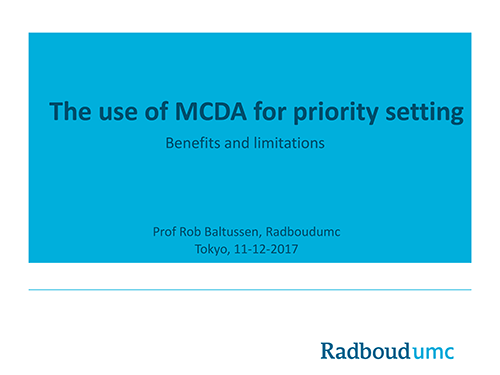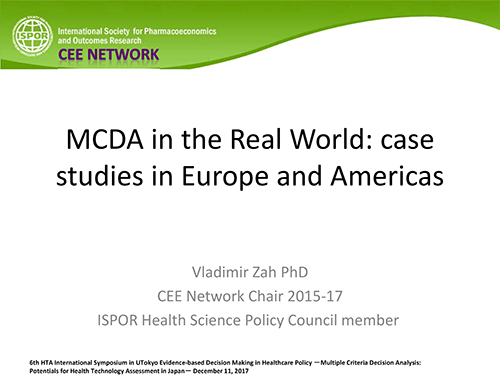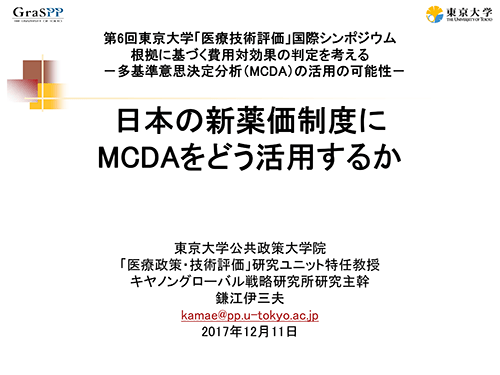2019年度から本格運用された医療技術評価制度。
その研究における産官学プラットフォームとしての役割を担い、
専門知識と実践的能力を兼ね備えた次世代リーダーの育成を目指すプロジェクトです。
「医療政策・技術評価」研究プロジェクト
Health Policy & Technology Assessment Research Project
2025年度医療技術評価国際シンポジウム
「医療技術評価制度は何を目指すか―発展の方向性と課題―」
医薬品・医療機器の費用対効果評価に基づく価格調整制度は、2019年度に制度化され今日に至っています。当大学院では、そのような制度の制度改革に対応して、医療技術評価の高度な専門性をもった人材を養成すべく「HTAエキスパート養成プログラム」を2017年度から開講してきました。
本シンポジウムでは当該プログラムの9年間の成果を振返るとともに、日本における医療技術評価制度の発展の方向性と課題について理解を深める。
| 日時 | 2025年12月3日(水)15:30 – 18:30 |
|---|---|
| 主催 | 東京大学公共政策大学院 医療政策・技術評価研究ユニット |
| 共催 | キヤノングローバル戦略研究所 |
プログラム
| 15:30-15:33 |
開会挨拶
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:33-15:36 |
共催挨拶
|
||||||
| 15:36-15:55 |
報告:「HPTAプロジェクト及びHTAエキスパート養成プログラムの9年間」
|
||||||
| 15:55-16:30 |
招待講演1: 「日本の医療技術評価制度 – ビジョンと期待」
|
||||||
| 16:30-17:05 |
招待講演2: 「韓国の医療技術評価制度 – 教訓と課題」
|
||||||
| 17:20-18:25 |
総合討論: 「日本の医療技術評価制度をどう発展させるか」
|
||||||
| 18:25-18:30 |
閉会挨拶
|
2020年度医療技術評価国際シンポジウム
「新型コロナパンデミックと医療技術評価の役割」
2019年4月に、中医協では医薬品・医療機器の費用対効果評価に基づく価格調整、いわゆる医療技術評価の方策が制度化された。しかし、医療技術評価は、単に薬価調整のためのツールだけではなく、価値に基づく医療を実現する政策としての意義を有している。一方、世界は、昨年来の新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックにより、医療や経済はもとより、あらゆる方面で危機に直面している。
本シンポジウムでは、新型コロナパンデミックと医療技術評価の役割について考える。
| 日時 | 2021年3月2日(火)16:15-19:35 |
|---|---|
| 主催 | 東京大学公共政策大学院 医療政策・技術評価研究ユニット |
| 共催 | キヤノングローバル戦略研究所 |
| 後援 | 武蔵野大学国際総合研究所 |
プログラム
| 16:15-16:20 |
開会挨拶
|
||
|---|---|---|---|
| 16:20-16:30 |
背景と論点
|
||
| 16:30-17:00 |
講演1:COVID-19 and health economics / HTA challenges in a Swedish perspective
|
||
| 17:00-17:30 |
講演2: Covid-19 pandemic and Health Economics in France Pierre-Yves Geoffard, Professor, Paris School of Economics
|
||
| 17:30-18:00 |
講演3:Case Report from Asia – Covid-19 pandemic and HTA in Taiwan
|
||
| 18:00-18:30 |
講演4: COVID-19 & Future of Health Economics
|
||
| 18:40-19:30 |
総合討論 Role of Health Technology Assessment in the era with Covid-19
|
||
| 19:30-19:35 |
閉会挨拶
|
2019年度 医療技術評価国際シンポジウム
「医療技術評価の制度化ーその論点と今後の方向性」
3年前に中医協により試行的に導入された医薬品・医療機器の費用対効果評価に基づく価格調整の方策が、本年4月より制度化されるに至った。一方、昨年来財務省は、経済評価を価格調整だけでなく保険適用の可否判断に使うべきとの考え方に立ち、保険収載が見送られる医薬品に対応する新たな保険外併用療養費制度など、さらなる改革を提案している。
そこで、本シンポジウムでは、そのような2省の考え方の違いをふまえて、医療技術評価の制度化の意義と論点について考える。
まず午前のセッションでは、海外より2名の専門家をお招きし、英国をはじめとする海外の医療技術評価の最新事情を知り、価格調整か適用判断かの異なる論点がどのように展開されているかを学ぶ。午後のセッションでは、厚労省の見解を迫井審議官から、また、財務省側の主張を踏まえた見解を公共経済学が専門の小黒教授から解説していただく。
さらに総合討論では、各専門家の講演を受けての討議を通して、制度化後のビジョンや方向性を中心に、今後の医療制度改革の課題について理解を深める。
| 日時 | 2019年12月3日(火)10:55-14:45 |
|---|---|
| 会場 | 福武ホール 福武ラーニングシアター (地図) |
| 主催 | 東京大学公共政策大学院 医療政策・技術評価研究ユニット |
| 共催 | キヤノングローバル戦略研究所(CIGS) |
| 後援 | 武蔵野大学国際総合研究所 |
プログラム
| 10:55-11:00 |
開会挨拶
|
||
|---|---|---|---|
| 11:00-11:10 |
背景と論点
|
||
| 11:10-11:40 |
講演1: 医療技術評価:日本は英国の成功と失敗から学べるか
|
||
| 11:40-12:10 |
講演2: 国際的視点からのHTAの展望
|
||
| 12:10-12:50 | 休憩 |
||
| 12:50-13:15 |
講演3: 費用対効果評価‐制度化の背景と課題
|
||
| 13:15-13:40 |
講演4: 医療保険財政を巡る現状と課題
|
||
| 13:40-14:40 |
総合討論「新制度の展開に必要な今後のビジョンは?」
|
||
| 14:40-14:45 |
閉会挨拶 福井俊彦 キヤノングローバル戦略研究所理事長 
|
第6回 医療技術評価 国際シンポジウム
根拠に基づく費用対効果の判定を考える
-多基準意思決定分析(MCDA)の活用の可能性-
世界では昨今、医療技術評価を公共政策として制度化する動きが加速されている。安倍内閣は、既に「日本再興戦略」改訂2014に費用対効果の検討を明記し、新制度の導入を国家の既定路線としている。2012年5月より始まった厚生労働省の中医協による医療技術評価の検討は、2016年度より試行的に導入され、さらに2018年度よりの本格的導入が予定されている。
まだ、新制度の内容の細部は検討中ではあるが、医薬品の費用対効果の判定や、その結果の薬価への反映の意思決定プロセスは、できるだけ透明であることが求められる。そのためには、客観基準を明示したルールの策定が望まれる。
そこで本シンポジウムでは、近年、そのような目的にかなうものとして、欧米の医療技術評価で注目されている多基準意思決定分析(MCDA)の手法について基本を学ぶ。そして、わが国への応用の可能性について考える。
| 日時 | 2017年12月11日(月) 13:20 - 18:00 |
|---|---|
| 会場 | 東京大学 福武ホール地下2階 福武ラーニングシアター(地図) |
| 主催 | 東京大学公共政策大学院「医療政策・技術評価」研究ユニット |
| 共催 |
|
| 後援 | 明治大学国際総合研究所 |
| その他 |
|
プログラム
| 13:20-13:30 |
開会の挨拶
|
||
|---|---|---|---|
| 13:30-14:10 |
講演1「MCDAの基本:医療技術評価への応用の利点と限界」
|
||
| 14:10-14:50 |
講演2 「MCDAの実際:欧州や北米における事例について」
|
||
| 14:50-15:00 | 休憩 | ||
| 15:00‐15:40 |
講演3 「日本の新薬価制度にMCDAをどう活用するか」
|
||
| 15:40-16:20 | 休憩および参加者意見交換 | ||
| 16:20-17:50 |
パネル討論会 司会 城山英明 東京大学法学政治学研究科・公共政策大学院 教授 パネリスト

|
||
| 17:50-18:00 |
閉会の挨拶 福井俊彦 キヤノングローバル戦略研究所理事長 |