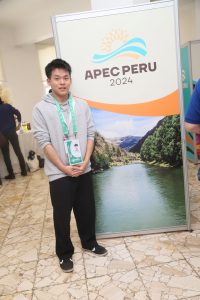11月10日から11月15日の間、日本から地球の裏側にあるペルーにて、15エコノミーから集まった80人の若者とAPEC Voices of the Future(以下APEC VOF)に参加したことは私にとって名誉なことでした。現在のリーダーたちの発言に耳を傾け、未来のリーダーたちと強固な関係を築く機会を、温かな人々と多様な文化が存在するペルーで得られたことは、私にとって忘れられない経験と思い出となりました。
APEC Voices of the Future とは

APEC VOFは、21のAPEC加盟エコノミーから選ばれた若手リーダーや教育者のチームが毎年集まり、APECサミットに参加するイニシアチブです。このプラットフォームでは、若者の代表者たちが、APECのビジョンや目標に関する自らの意見を、APEC の首脳、高官、ABACメンバー、さらにはビジネス界のCEOなどの主要な関係者に直接伝えることができます。
APEC VOFのテーマは、実際のAPECのテーマに沿っています。今年のテーマは「Empower, Include, Grow」でした。APECは日本語で「アジア太平洋経済協力」と訳されます。APEC VOFでも、その言葉の通り、経済協力の観点からテーマに沿った議論が行われました。
また、APEC VOFは若者がAPECプロセスに新しい視点や洞察を提供できるという理念に基づいており、地域の発展に向けた潜在的なパートナーシップや協力を促進する場でもあります。プログラムの前半ではAPEC VOFとしての共同宣言の起草や議論が行われ、後半では APEC CEOサミットの全てのプログラム参加する機会が設けられています。
APEC Voices of the Futureでのプレゼンと共同宣言

APEC VOFでは、プログラムの最初に全てのエコノミーがプレゼンテーションを行う機会が設けられていました。一部のエコノミーは高校生のみを派遣していることもあり、各エコノミーが注目するテーマに違いが見られました。例えば、文化に焦点を当てるエコノミーがある一方で、自らの経済状況や課題に注目するエコノミーや、自エコノミーの政策をAPECの枠組みに反映させているエコノミーもありました。
私は最初に、日本経済の課題として高齢化社会やエネルギー依存度の高さを指摘し、これに伴うサプライチェーンの脆弱性について述べました。次に、これらの課題に対応する日本の戦略として、CPTPPを通じたルールメイキングやサプライチェーンの多様化とアジア太平洋地域との関係強化の重要性を挙げました。また、さらに、APECは経済的な議題を中心とするフォーラムですが、地政学や地経学の観点から、政治的事柄についても議論すべきであると述べました。経済協力を推進する中で、地域の安全保障や地政学的な動向を無視することはできず、これらを含めた包括的な議論が必要であると強調しました。最後に、若い世代が平和と共存を目指し、協力による持続可能な経済成長と安定の実現を追求する重要性を強調しました。
APEC VOFでは、共同宣言が発出されました。この宣言は、参加したすべてのエコノミーの代表者が同意して作成したものです。APEC の取り組みは、自主的、非拘束的、そしてコンセンサスに基づく協力が特徴的です。共同宣言の起草過程においても、すべての取り決めに関して全てのエコノミーの挙手による同意が必要とされました。そのため、細かな言葉の選び方や考え方の違いによって、議論が進まない場面もありました。これは実際の国際会議ではさらに対立が深まる場面もあるだろうと思います。私は、原案に含まれていなかったFTAAPへの言及と、東京大学にもあるCampus Asiaのような学生の留学を促す枠組みを APECでも作ることを提案しました。
後から見返すと、若者主導で社会的課題をボトムアップで解決しようとする内容が多い印象でした。特に、枠組みやプラットフォームを作るという提言が多く見られました。例えば、ABAC レポートでは既存の枠組みや協定を強化し、それを活用することに重点を置いています。一方で、APEC VOFでは、若者ならではの新しい視点から新たなフレームワークを求める意見が多く出されました。以下に、共同宣言の結論を示します。

私たちAPECの若者は、すべての人々と地域社会が繁栄できるエンパワーメントされた、包括的で成長志向のアジア太平洋を構想しています。APECリーダーに対し、脆弱な地域社会を支援し、包括性を育み、地域全体の持続可能な発展を推進する政策を実施するよう呼びかけます。団結と共有されたコミットメントにより、すべての声が力を持ち、社会的および経済的機会が包括的であり、すべての成長が持続可能な未来を構築できます。
APEC CEO サミットについて
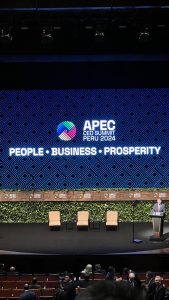
APEC CEOサミットとは、APEC加盟エコノミーのリーダーやグローバル企業のCEOが一堂に会し、地域経済協力、貿易・投資の促進、イノベーションやサステナビリティなどの重要課題について議論する年次イベントです。APEC VOFの参加者は、特に制約もなくこのサミットに参加することができました。このサミットでは、政策立案者と民間セクターの対話を深め、公私連携を強化し、持続可能な経済成長やビジネス機会の創出を目指しています。
今年は劇場で開催され、劇場内では各エコノミーの首脳や経済界のリーダーによる講演やシンポジウムが行われました。また、劇場外にはネットワーキングスペースが設けられ、ビジネス関係者との対話が可能でした。日本からは、ペルーや南米に支社を置く企業の関係者が参加していました。各エコノミーの首脳は、自エコノミーの APECにおける取り組みや自エコノミーのビジネス的魅力について語っていました。一方で、経済界のパネリストは、ビジネスの観点から見た現在の世界情勢や、それに伴うチャンスとリスクについて議論していました。
特に印象的だったのは、どのパネリストも地政学的な情勢とリスクに言及していた点です。昨今の貿易体制の不透明性や地政学的な変化は、経済、政治、安全保障に大きな影響を及ぼしており、これらのリスクはエコノミーだけでなく、企業にとっても無視できない課題となっています。特に、サプライチェーンの脆弱性や資源の国境を越えた移動、AIやデジタル技術の格差がもたらすリスクが強調されていました。私は、このような情勢下での国際的な協力とルールに基づく秩序の重要性をこれまで以上に強く実感しました。
また、APECに関する議論では、組織としての魅力をどのように維持し、加盟エコノミー間の多様な声をまとめ上げるかが重要なテーマとして挙げられていました。特に、若者の視点を政策形成に取り入れ、次世代が直面する課題に対応することの重要性が強調されていました。APECは単なるサミットではなく、包括的で実行可能なビジョンを持ち、それを具体的な政策として実現していくことが求められています。その際には、データに基づいた政策の裏付けが重要であり、証拠に基づく議論や意思決定が、包括性と持続可能性を支える鍵となると指摘されました。また、私はAPECが加盟エコノミーの経済統合や地域の安定に果たす役割を再確認し、その長期的な持続可能性を確保するための新たな戦略が必要であることも改めて認識しました。
ペルーについて
ペルーでは、人々から温かい歓迎を受けました。ペルーと言うと、マチュピチュやアルパカの姿を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実際には非常に多様な文化が存在しています。ペルーには、リマをはじめとする沿岸エリア、アンデス山脈を代表とする高地エリア、アマゾンを代表とする熱帯雨林エリアがあり、地域ごとに文化的特徴が異なります。
また、50近くの民族が存在しており、民族集団ごとに文化が異なる点も特徴的です。さらに、日本や中国などの移民の影響を受け、東アジアに近い食文化も見られます。特に、生のマグロを使用したセビーチェは絶品でした。これまでに 10カ国以上を訪れましたが、ペルーはトップレベルに入る、また行きたい場所の一つとなりました。
自分の状況
私は日本を代表して、たった一人でAPEC VOFに参加しました。この状況は、他のエコノミーの代表団とは異なっていました。私にはエデュケーターがいませんでした。他のすべてのエコノミーではエデュケーターが存在し、どのエコノミーも最低でも2人以上、多い場合では5人以上のメンバーを派遣していました。しかし、この状況は私にとって弱みではなく、むしろ強みとなりました。
私はしがらみを感じることなく、自由に各エコノミーの代表団の人々と交流することができました。また、私が一人で参加していることを知っている周囲の方々が、積極的に私を自分たちのグループに迎え入れてくれました。ある日は台湾の代表団のテーブルで食事をし、また別の日にはニュージーランドの代表団のテーブルで食事を共にしました。
そして何よりも、私の「兄弟」であるペルーの代表団の方々からは、温かい歓迎と丁寧な案内をいただきました。彼らの厚意には、いくら感謝してもしきれません。
日本の状況

世界の会議に参加することで、日本が世界からどのように見られているかを実感することができます。日本は世界から高く評価されており、日本人であるというだけで好印象を持たれる機会が多いです。また、多くの人が日本のアニメやマンガに関心を持っており、これらの話題がしばしば中心に上がることが印象的でした。一方で、真面目な議論としては、日本の有名な企業や産業、技術についての話題や、日本の若者の役割、さらには少子高齢化に関する議論が頻繁に取り上げられました。
特に印象的だったのは、北米のエコノミーの人々とラテンアメリカのエコノミーの人々が日本語で会話をしていたことです。彼らは日本語を学んでいたようで、その会話には私自身は参加していませんでした。それでも日本語で話が行われていたという事実は、日本が世界で影響力を持つエコノミーであることを示しています。このような人々に引き続き日本に関心を持ってもらうことも考えるべきポイントであると感じました。
最後に

来年のAPECの開催は大韓民国であり、開催都市は慶州です。私は以前、慶州を訪れたことがありますが、この都市はのどかな風景の中に豊かな歴史が詰まった素晴らしい場所でした。来年のAPEC VOFが再び成功することを心より祈っています。
最後に、派遣前に貴重なお話を聞く機会をいただいた ABAC 日本支援協議会の皆様と外務省APEC室の皆様に深く感謝申し上げます。また、私に貴重な機会を提供してくださった西沢先生と、私の渡航を事務的に大変ご支援いただいた大野さんにも心より感謝いたします。