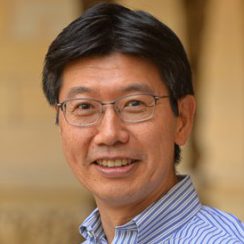ゼロ価格効果は、行動経済学で多くの注目を集めてきた。しかし、これまでのところ、実験ではなくフィールドデータを使用しゼロ価格効果を示した研究は少ない。これは主に、同一市場においてゼロ価格の近傍で複数の価格変化を観察することが難しいためである。研究チームは、日本全国の地方自治体が、子供医療費の自己負担率をゼロから3割の様々なレベルに設定していることを利用し分析を行った。分析対象は7歳から14歳までで、各自治体の自己負担割合のデータと、2005年から2015年までの患者レベルの月次医療費データとを結合し分析した。差分の差分法(DID)という分析手法を用い、ゼロ価格を含む医療費の自己負担が医療需要に及ぼす影響を推計した。

Image by pch.vector on Freepik
分析結果から、ゼロ価格効果は存在し、ゼロ価格需要を非連続的に押し上げる特別な価格であることが明らかとなった。自己負担を無料からごくわずかの金額に引き上げると、最低月1回受診する確率が4.8%減少した。この削減効果は、自己負担をゼロから1割に引き上げた場合の医療費削減効果の約半分であり、大幅なものである。この結果は、価格をあえてゼロとすることで、小児の予防接種などの高価値で費用対効果の高い医療の需要を一層押し上げることができることを示している。一方、価値の低い医療については、無料ではなく少額の自己負担を課すことでそれらの利用を一段と減らすことができる。
また、少額の自己負担がどのような患者に影響を及ぼすかを分析したところ、比較的健康な子供の頻繁な受診が29.7%減少することがわかった。一方、少額の自己負担は、病状の重い子供が最低月1度受診することを妨げなかった。これらの結果は、少額の自己負担が患者のスクリーン(選別)に役立ち、医療をより必要とする人に資源を割り当てる役割を果たすと解釈できる。
さらに、消費者が商品やサービスのメリットとコストを誤って認識するという問題(行動ハザード)について、いくつかの高価値および低価値の医療を例に分析した。まず、無料ではなく、一回200円の自己負担がある場合、うつ病、ADHD、タバコ、肥満などに対する医療(価値の高い医療)が10%減少した。逆に言うと、自己負担をなくし価格をゼロとすることで、これらの価値の高い医療を一段と増やすことができる。一方、気管支炎や喘息に対する抗生物質の不適切な使用(価値の低い医療)も、一回200円の自己負担で18.3%減少した。これらは、少額の負担により価値の高い医療も低い医療も需要が大きく減少することを示し、患者は必ずしも医療の価値を正確に理解していないと考えられる。従って、価値の高い医療については価格をあえてゼロにし、価値の低い医療の場合は、ゼロ価格を避け少額の自己負担金を選択するなど、ゼロ価格と非ゼロ価格を政策目標に応じて慎重に選択することが重要となる。